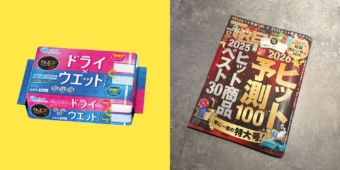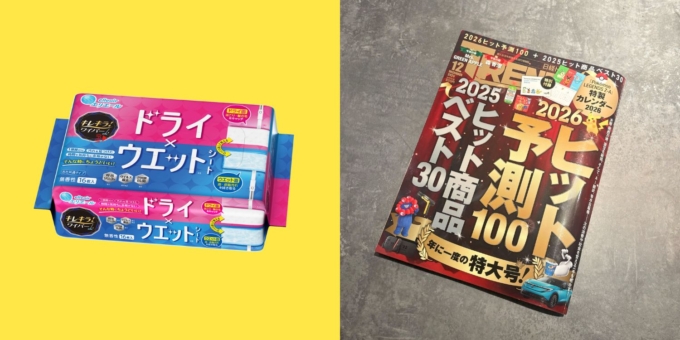【BG×サニーサイドアップ】“土”を起点に“食べ手”と“つくり手”をつなぐ新たな農業・食のモデルのPRとは

近年、猛威を振るう異常気象の中で、野菜価格の高騰や不作のニュースを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
株式会社BGは「BLACK TO GREEN|今までにない視点で農業のまだ見ぬ価値を発見し、社会に共有し続ける」をミッションに掲げる次世代農業ベンチャー。「土」を起点に、「つくり手」と「食べ手」を結ぶ新たな時代のフードシステムを構築するために2021年に創業しました。
サニーサイドアップは、同社の掲げるミッションに共感。新しい食と農の運動「Next Green Revolution」の始動にあたり、サービスローンチ前の2025年3月から現在に至るまで、PR・コミュニケーションを担当しています。

両者の取り組みがどのようなものだったのか。株式会社BG COOの久保田龍星さんとサニーサイドアップの俊成和東の2人に、出会いから共創のプロセス、今後の展望などを語っていただきました。
Next Green Revolutionをパーパスに農業の新たな価値を共有
――お2人はそれぞれ、どのようなお立場でいらっしゃるのでしょうか。
久保田さん:わたしは株式会社BGでCOOをしています。経営全般だけでなく、PR戦略の実行もサニーサイドアップさんと二人三脚で進めています。

株式会社BG COO 久保田龍星さん
俊成:サニーサイドアップのパブリックリレーション事業部1局1部のリーダーをしておりまして、BGさんと一緒に取り組むにあたって、窓口を担当しました。
――BGでは「土」に着目したプロジェクトに取り組んでいらっしゃるとのことですが、土の課題に気付いたきっかけは?
久保田さん:農業や地球の持続性の課題の解決に向けて、収穫量やおいしさ、そして環境への配慮 のすべてを諦めない、“トレードオフのない農業”を数十年に渡り実践してきた全国の農家を訪ね歩く中で、共通の鍵となっていたのが “土” の存在でした。
どの農家も、畑の土を自然界が本来持っている多様な土壌生態系に近づけることで、野菜はよりおいしく、健康に育ち、安定した収穫へとつながっていました。その気づきがわたしたちの原点です。
俊成:BGさんの取り組みを知った時は、唯一無二のアプローチをされていると感じましたし、個人的にも非常にワクワクしたことを覚えています。ただ、まったく新しい着眼点でアプローチされているので、生活者のみなさまにどうやって共感していただくのか、かなり頭を悩ませました。

サニーサイドアップ 1局 リーダー 俊成和東
わたし自身も農業に詳しいわけではなかったので、実際に畑を借りて農業を体験してみるなどして、少しずつ知識を深めていきました。
久保田さん:実際に土に触れて体験してくださる俊成さんを含めたサニーサイドアップの姿勢が、本当に嬉しかったのを覚えています。
――現代の日本が抱えている土の課題とはどのようなものでしょうか。
久保田さん:この夏も非常に厳しい暑さが続きましたが、ここ数年で異常な気候変動はもはや身近なものになりました。野菜の生育にも大きな影響が出ており、品薄や価格高騰などの問題が起こっています。その背景には長く続く化学肥料への依存と、それに伴って進んでいる土壌の劣化があります。
化学肥料はいわば植物に直接栄養を与えるようなもので、土を経由しません。それに過度に依存し、土づくりが疎かになってしまったことで、結果的に土の中の微生物や有機物が減り、砂のような土壌になり固くしまるため根は浅く、水も通らない土になってしまいます。そのために、高温や豪雨など気候変動の影響を強く受けやすくなります。
――今後、さらなる気候変動が予測される中で、土の課題を解決できなければ、おいしい野菜が食べられなくなってしまいそうですね。
久保田さん:そうなんです。やっぱり人はおいしいものを食べたいという根源的な欲求がありますよね。そして、おいしい野菜を作るということは、よい土をつくっていくということです。

よい土は、見た目も違いますし、微生物のコミュニティ、つまり生態系がとても多様で、地球にとってもすごくよい環境になっています。つまり、人がおいしいものと食べたいということと、地球によい土づくりということは、同じベクトルです。しかしながら、今の日本には土を強くする仕組みがありません。
――だからこそ、土を強くしていくようなフードシステムの構築が必要なんですね。
久保田さん:わたしたちは、「食べる革命|Next Green Vegetables」と「つくる革命|Next Green Method」という2つの仕組みを通じて、次世代のフードシステムをつくる「土の革命|Next Green Revolution」を目指しています。

おいしい野菜を食べることが、地球にもいい土につながるそれが本来の農業が持つ価値です。この「Next Green Revolution」というプロジェクトと、それを社会に実装していくための仕組みを、7月10日にサニーサイドアップさんにサポートしていただき、リリースしました。わたしたちは、土を起点に“つくる人”“食べる人”“企業”などあらゆるステークホルダーをつなげていく取り組みを始めています。
――サニーサイドアップとパートナーシップを結ぶ決め手となったのはどのようなところでしたか?
久保田さん:わたしたちのビジネスパートナーから、社会課題とブランドを繋いでくれるようなPRを行うブランドコミュニケーションエージェンシーがあるよ、と紹介されたのがサニーサイドアップでした。
実際にお話しをしてみると、PRのプロとしてのスキルはもちろんですが、わたしたちの「土を起点に社会を変えていく」という理念に強く共感して、「Next Green Revolution」の実現をともに目指してくれると感じたから。もちろん、メディアに対してのリレーションや企画力という部分もポイントでしたが、未来に対しての課題や危機感を共有できる、ビジネスを超えた仲間というところが、一番の決め手でしたね。
BG×サニーサイドアップの取り組み
――パートナーとして、どのような取り組みをしていったのでしょうか。
俊成:正直なところ、最初は「土をPRする」という発想に驚かされました。詳しく話を聞いていくなかで「おいしいものを食べることが、結果的に土を良くし、地球にいいことにつながる」という考え方に、すごく共感したんです。PRの視点から考えても、社会がポジティブに関わるテーマだと思いました。

ただ、同時に“見えないものをどう伝えていくか”という難しさも感じました。生活者のみなさんは、作物や料理の見た目には興味を持っても、その手前にある“土”まではなかなか意識が届かない。どうやって“自分ごと”にしてもらうかがカギになると考えました。
――実際に、BGさんが協力している農園にも足を運ばれたそうですね。
俊成:畑に伺って生産者さんの話を聞きました。みなさん、自分の畑にものすごく誇りを持っていらっしゃって、知識量もものすごく深い。“農業マニア”と呼びたくなるほど、土や気候、微生物などについて熱心に語ってくださったんです。
そんな方々が作る野菜はやっぱり本当においしくて、「この取り組みをもっと世の中に伝えたい」と強く思わされました。
久保田さん:サニーサイドアップのみなさんは、畑に来て土に触れて、食べて、感じた上で議論をしてくださるんです。それがすごく心強かった。お願いしているPR会社というよりも、同じゴールに向かう仲間という感覚でした。
――具体的にはどのようなPR活動を展開したのでしょうか。
俊成:まず3月から3カ月ほどかけて、BGさんとともに全体戦略を設計しました。ターゲットは3層構造で「生活者」と「生産者」、そして「企業」です。
特に企業は、土の価値を事業成長に活用する側として“参画したくなるストーリー”を描くことが目的でした。5月から6月にかけては、久保田さんとともにメディアキャラバンを実施。報道向けの資料を用意し、メディア各社に直接訪問してプロジェクトの説明を行いました。
久保田さん:わたしたちは、それまでメディアと向き合う経験がほとんどありませんでした。なので、“社会への伝え手”の方々とどう対話すべきかは、サニーサイドアップのみなさんと一緒だからこそ考えることができました。

何度も中間報告をして、反応を見てメッセージを磨いていく。単発の発表としてではなく、理解を育てるプロセスとなるように積み上げていきました。
俊成:7月には発表会を開催して、土壌実験や野菜の試食など体験型のコンテンツを組み込みました。どのコンテンツも「Next Green Revolution」の仲間になってもらうことを意識して設計しました。
――メディアや世間の反応はいかがでしたか。
俊成:発表会当日には29社のメディアに来ていただくことができました。参加した方々からは「こんな発表会は初めて」「お世辞抜きで一番いい発表会でした」という声を複数いただいて、嬉しかったです。

その後も取材依頼が相次ぎ、キャラバンがそのまま記事化されるようなケースもありました。
久保田さん:ある記者さんから「土という視点が新しい」と言われたんです。わたしたちにとっては当たり前のことでも、社会にとっては“再発見”なのだと気付かされました。当たり前のものが当たり前じゃなくなった今だからこそ、本質的なものに新しさが宿るんですね。それを発見し、社会にベネフィットのある形で届けることこそが、この活動の意義だと思っています。
――苦労したことや印象に残っているエピソードはありますか。
久保田さん:もう、全部が大変でしたね(笑)。特に発表会は、わたしたちにとって初めての大きなステージです。これまでの成果を初めて世の中に出す機会だったので、「この時間でわたしたちの会社のキャラクターが決まる」と思っていました。直前まで毎日、練習していましたよ。
俊成:恋人でもここまで連絡を取らないよ、っていうくらいには連絡を取り合っていましたね(笑)。でもそれくらいの熱量で共有できていたからこそ、いい形で発表会に繋げられたと思います。形式的なクライアントとエージェンシーの関係ではなく、お互いに率直な声を伝えあえる関係でした。
久保田さん:まさにそうですね。普通なら気を遣って言えないようなことも、自然に意見交換ができました。それは、仲間としての距離感だったからこそだと思います。

これからのミッション
――今後のビジョンやミッションについてお聞かせください。
久保田さん:これからは「Next Green Revolution」を社会に実装していくフェーズに入ります。来年前半には、“おいしい理由がわかる野菜ブランド” 「Next Green Vegetables」を正式にリリースする予定です。実は地球にもいい、おいしい野菜、という新たな選択肢を、日常に根付かせていきたいですね。
そして、2030年には誰にとっても確かな選択肢となることが目標です。そのために、「Next Green Method」によって生産者の方と土から強い産地を創出し、Agri LCA+という可視化技術をはじめとして、農業と他産業をつなぐ循環システムを確立していきます。
俊成:PRとしても、発表して終わりではなく、伝えたことを育てていくことが大切だと考えています。メディアや生活者のみなさんに共感していただき、その共感が広がる仕組みづくりを一緒に取り組んでいきたいです。
――Agri LCA+とはどのような技術なのでしょうか。
久保田さん:Agri LCA+は土壌の価値を可視化する日本初の仕組みです。これには、国立研究開発法人産業技術総合研究所と共同で開発した環境影響評価スキームが組み込まれています。農業の営み全体を総合的に評価することで、野菜のおいしさや健康に寄与する土壌、環境負荷の小さい土壌など、目的に応じてさまざまな角度から土壌の価値を可視化することが可能になります。農業が本来持つ価値がわかる、使える形に可視化することで、誰もが自分のできることから農業、食、そして地球の未来づくりに参加できる社会を、土から実現したいと思っています。
――これまでの取り組みを振り返って、どのような想いでいらっしゃいますか。
俊成:このプロジェクトを通じて、PRとは共創の場づくりだと改めて感じました。理解を育てる時間を共有することで、メディアも生活者も仲間になっていく。今回のプロジェクトは、BGさんの高い熱量があったからこそ、僕らも全力で走り切れたと感じています。
久保田さん:“食べる人”“つくる人”“伝える人”、そのすべてがこの「Next Green Revolution」の一部です。おいしい野菜をたべることが、土を育み、地球を育む。そんな“おいしい循環”を、社会のあたりまえにしていくこと。それが、わたしたちBGの目指すNext Green Revolutionであり、今後も全力で取り組んでいきます。

株式会社BGでは今後も、みんなの様々な日常へおいしい循環をつくっていきます。その第一弾が、おいしい理由のわかる野菜ブランド「Next Green Vegetables」。スーパーの店頭などで、このロゴを目にした際は、ぜひ足を止めてチェックしてみてください。

後日、スマイルキーパー協力のもと、 「Next Green Vegetables」の新鮮なにらや小松菜を卵とじに🌱「瑞々しさや香りが全然違う!」と大好評でした。
サニーサイドアップはさまざまな商品・サービスのPR・コミュニケーションを手がけています。
コミュニケーションの力で、どんなことが実現可能なのか?そんなご相談からでも大歓迎です。ぜひお気軽に下部の「CONTACT」ボタンからお問い合わせください。